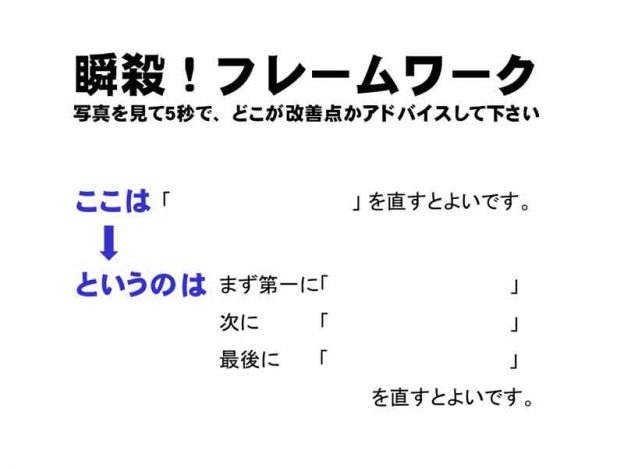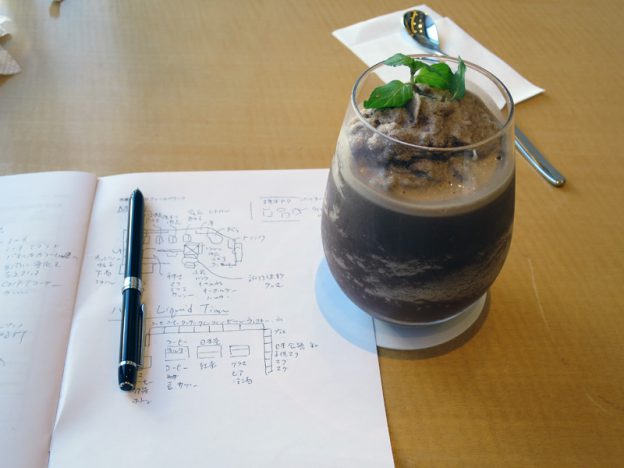瞬殺!!VMD5秒トレーニングについてお話します。
これ、VMDのゲームみたいなもので、去年からわが社で
取り入れている研修コンテンツです。
瞬殺というのは、サッカーに例えるとサドンデスみたいなものです。
点が入るとゲームセット!!っていうやつですね。
同じように、5秒で売場のどこが悪いか言えないと失格!!
というやつです。
これ、受講生にけっこうウケていて、楽しいっていう人も多いです。
VMDインストラクターの方はぜひやってくださいね。
ご存知の通り、VMDインストラクターは、55のフレームワーク
という引き出しがあって、売場づくりを指導する際に、
それをいかんなく発揮しています。
つまり、売場づくりの欠点を瞬時に見抜き、頭の中の引き出しに
収納しているフレームワーク用語を使って、売場スタッフに
指導します。
フレームワーク用語があると、抽象的な言葉ではなく、詳細で正確な
指導ができるというわけで、VMDインストラクターの武器になっています。
例えば、壁面の陳列状態を見て、
●IPとPPのメリハリ
●フェイシング
●くくり
●カラーライゼーション
などの用語がポンポン頭の中の引き出しから飛び出て来る・・・
というわけです。
それを現場スタッフに伝えればいいのです。
もちろん、売場スタッフにVMD習熟度がない場合は、やさしい言葉に
置き換えて指導しますが、ある程度VMD教育がなされている売場は
これら専門用語で十分通用します。
これを写真でやるのが、瞬殺!!VMDトレーニングなんです。
やり方は下記です。
- 直しがいのある売場の写真をひとつスライドに出す。
- 「どこを直せばいい? 5秒見てから、なるべくフレームワーク用語で言って」
と講師は言う。 - 講師は5秒、声に出してカウントする。
- 受講生はまずフレームワーク用語を言ってから、直し方の詳細を言う。
- 講師はそれを聞いて正す。
こんな感じ。
特に4がおもしろいです。
受講生は、「ええっと」とか言いながら、
「くくりが不鮮明ですね」と言い、
「紅茶売場のくくりがわからないので、どこがアッサムでダージリンなのか
カタマリをつくって、カタマリとカタマリの間に
ネガティブスペース10cmほど空けるといいですね」
などと言えば、瞬殺は勝利!!
「次はPOP編集が違うかな・・・」
「というのは、プライスカードと商品説明POPが混ざり合って、
どの商品を指しているのか、わからないので」
「プライスカードは商品のカタマリの真ん中に設置、
商品説明POPは、カタマリの左側に立てます」
などと言えば、瞬殺は受講生の勝利!!です。
(ここまで言えると一級モノです)
これ、最近のVMD初心者研修でもやり始めていて、
自分たちの売場の写真を瞬殺!!トレーニングに使うと、
「あー、やられたなー」みたいに現場スタッフは納得してくれます。
そして、研修終わった後も、受講生が
「ネガティブスペース!!」
「PPとIP!!」
「リピテーション!!」
と口ずさみながら暗唱している風景を見ます。
こういう初めての用語を自在に使えると言うことは、
受講生にとっておもしろいんです。
用語は専門用語なので、研修のやった~!!感も醸成できます。
確かに、「専門用語覚えても、意味はない」とおっしゃる方も
いると思います。
しかし、専門用語を覚えると、生徒はわかった気になり、
専門用語を現場で口ずさむことによって、いつまでもフレームワークを
覚えてくれます。
さらに、本部やスタッフ同士のいつもの会話の中に入れていただくと
効果が増し、売場はVMDがキープされた状態を続けることができます。
たかが専門用語、されど専門用語。
そもそも専門用語がないと、VMDだけでなく釣りもヨガも上達しません。
VMDインストラクターの皆さん、ぜひVMD研修で
瞬殺!!VMD5秒トレーニング やってくださいね。(^^)
ちなみに、瞬殺は当社のメソッド「フレームワーキング」が
ベースとなっています。
(vmd-i協会事務局)